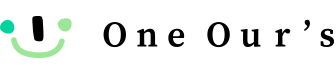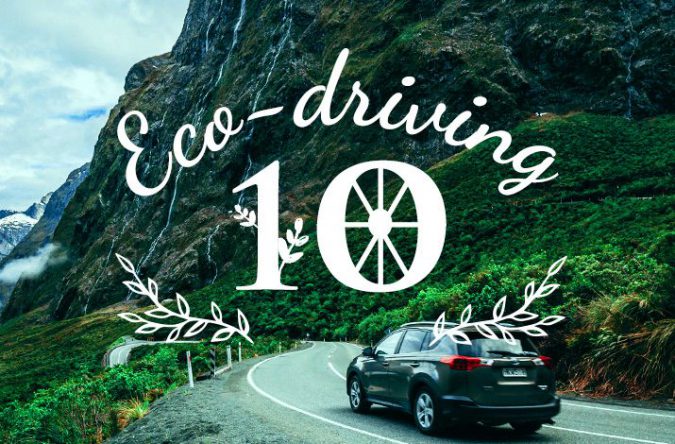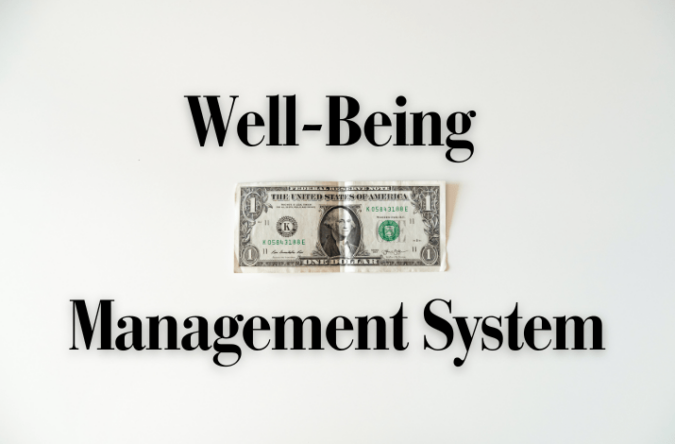投稿日:2024年12月16日/更新日:2024年12月16日
企業力向上には”健康経営”が要!概要や認定制度までわかりやすく解説

従業員が力を発揮するためには、常に健康な状態を維持できるかが重要です。
そこで重要となるのが、健康経営という考え方です。
では、健康経営とは一体どのような考え方なのでしょうか。
本記事では、健康経営の概要や認定制度について詳しく解説します。

健康経営とは?

健康経営とは、企業が従業員の健康管理を経営における課題としてとらえ、積極的に改善に取り組む施策のことです。
日本再興戦略や未来投資戦略に位置づけられており、国民の健康寿命の延伸に関する取り組みとして国として取り組んでいます。
メリットは、企業側が従業員の健康を増進することによって、生産性の向上や組織の活性化を見込める点。
健康に対して、個人だけでなく企業側も一緒に取り組む特徴があり、企業としてだけでなく個人の幸福度を向上させることも可能です。

健康経営による4つのメリット

企業が健康経営の仕組みを取り入れることで、以下4つのメリットをもたらします。
- 健康維持につながる
- モチベーションアップにつながる
- 定着率や長期化につながる
- 企業イメージアップにつながる
各メリットについて、詳しく解説します。
健康維持につながる
健康経営を取り入れることで、最も大きなメリットは健康維持ができる点です。
健康を維持できることで、従業員の体調が整い、集中力やパフォーマンスの向上が見込めます。
肉体的にも精神的にも安定して活動するためにも、健康経営が重要だといえるでしょう。
モチベーションアップにつながる
健康維持をサポートすることにより、従業員のモチベーションアップにつながります。
従業員の帰属意識を向上させることはもちろん、不要な心配や悩みを抱えることなく業務に集中して生産性を向上できる点が大きなメリット。
モチベーションアップにより、活気がある職場となり相乗効果によってさらなる改善を図れる可能性が高まるでしょう。
定着率や長期化につながる
働きやすい職場を構築できると、従業員の定着率向上や勤続年数の長期化が見込めます。
昨今、日本では働き手不足が深刻化しており、いかに従業員を確保できるかがカギとなっています。
人材確保に苦しんでいる企業にとっては、定着率の高さは大きなメリットとなるでしょう。
企業イメージアップにつながる
健康経営を実践することで、優良企業といったイメージを定着できるメリットがあります。
特に、健康経営銘柄や健康経営優良法人に認定されることにより、大きな効果を得られるでしょう。
従業員からの評価をはじめ、ステークホルダーやエンドユーザーにも効果がある点もポイントです。

健康経営に関連する3つの認証制度

健康経営に関連する認証制度として、以下の3つを紹介します。
- 健康経営優良法人
- 健康宣言事業
- 健康経営銘柄
各制度の詳細を見ていきましょう。
健康経営優良法人

参照:健康経営優良法人認定制度|経済産業省
健康経営優良法人とは、経済産業省が認定する「特に優良な健康経営を実践している法人を見える化する制度」です。
健康経営優良法人は日本健康会議で毎年認定しており、さまざまな企業が参画しているのが特徴。
認定を受ける際の基準として、以下の項目を満たす必要があります。
- 経営理念(経営者の自覚)
- 組織体制
- 制度・施策実行
- 評価・改善
- 法令遵守・リスクマネジメント
健康経営優良法人2024では、大規模法人部門に2,988法人、中小規模法人部門に16,733法人が認定されています。
健康経営優良法人に認定されると、認定書などを企業サイトや名刺などで使用可能です。
これにより、さまざまなインセンティブを受けられます。
健康宣言事業
健康宣言事業は、協会けんぽ・健康保険組合が創設した認証制度です。
健康宣言を行う企業の健康づくりを支援して、保険加入者の健康を増進させることを目的としています。
具体的には、事業所全体で健康づくりに対して取組むことを事業主が宣言し、その取組みについて協会けんぽがサポートする仕組みとなります。
参照:健康宣言|全国健康保険協会
健康経営銘柄

参照:健康経営銘柄|経済産業省
健康経営銘柄とは、国民の健康寿命の延伸を目的として創設された制度のことです。
健康経営に特に優れた実績を残している上場企業に対し、経済産業省と東京証券取引所が以下の基準を基に選定したうえで認定しています。
- 健康経営が経営理念・方針に位置づけられているか
- 健康経営に取り組むための組織体制が構築されているか
- 健康経営に取り組むための制度があって施策が実行されているか
- 健康経営の取り組みを評価し改善に取り組んでいるか
- 法令を遵守しているか
健康経営銘柄に認定されれば、企業のブランディングにつながるなどのメリットがあります。

健康経営を取り組むべき企業の特徴4選

健康経営に取り組むべき必要性が高い企業の特徴の特徴として、以下が挙げられます。
- 中高年の従業員が多い
- ストレスチェックの結果が良くない
- ヒューマンエラーや欠勤が多発している
- 人材が慢性的に不足している
それぞれ解説します。
中高年の従業員が多い
1つめは、中高年の従業員が多い企業ケースです。
年齢層が高ければ高いほど、何かしらの疾患が発症するリスクが増加します。
また、今後定年の65歳引き上げも控えているなかで、中高年でも働きやすい職場を構築し人街確保することが重要であり、健康経営への取組みは必須といえるでしょう。
ストレスチェックの結果が良くない
企業がストレスチェックを実施した際、結果が芳しくない場合は健康経営に取り組むのがおすすめです。
ストレスが増加すると疾患などが発症するリスクが高まるるため、医師による面接指導を促すなどのアクションが必要です。
ストレスは個人だけでなく、企業全体の問題として認識することが重要といえます。
ヒューマンエラーや欠勤が多発している
ヒューマンエラーや欠勤が多発している場合、健康経営に取り組むとよいでしょう。
労働環境が原因となり休業している場合、長期の休みを与えたとしても復帰したとしても再び体調を崩すリスクがあります。
そこで、健康経営を導入して従業員が働くことに対してストレスを感じにくい職場とできるかが重要です。
人材が慢性的に不足している
人材が慢性的に不足している場合も、健康経営が重要です。
たとえば休日出勤や残業が多くなると、身体に疲労が溜まり思わぬミスも発生しがちです。
健康経営の考えを取り入れて、業務量を調整する、人材確保や長期化に努めることで改善できるでしょう。

健康経営における具体的な施策5選

健康経営における具体的な施策として、以下が挙げられます。
- 健康診断や保健指導の実施
- ワークライフバランスの正常化
- 食事や運動習慣の正常化
- 社内コミュニケーションの促進
- 治療と仕事の両立を支援
それぞれ見ていきましょう。
健康診断や保健指導の実施
健康診断や保健指導の実施は必須の施策です。
また、定期健康診断の実施は法律で定められた義務でもあり、確実に受診できる体制を構築する必要があります。
ワークライフバランスの正常化
ワークライフバランスの正常化により、健康経営を実現することも重要です。
有給休暇の取得を推進したり、テレワーク勤務を導入したりすれば、私生活と仕事を両立しやすい体制の構築が可能です。
企業側としては、ノー残業日を設けたり、残業を事前申告制にしたりすることで、ワークライフバランスの正常化を図りやすくなります。
また、育児や介護などの短時間勤務制度や、週3日勤務制度を導入するなどの大がかりな対応も検討する余地があるでしょう。
食事や運動習慣の正常化
食事や運動習慣を習慣化できれば、心身の健康を維持できる場合が多いです。
そこで、食事や運動習慣の正常化を促す対策を実施するのがおすすめです。
運動クラブ活動のサポートや、スポーツクラブとの提携、外部事業者による栄養指導・相談窓口の設置などを行い、成果を上げた事例もあります。
社内コミュニケーションの促進
健診の受診・再診を周知するだけでなく、従業員を巻き込んだイベントを計画して社内のコミュニケーションを活性化するのもおすすめです。
競争が生まれる施策を実施すれば、従業員同士のコミュニケーションも生まれやすくなるメリットもあります。
従業員同士のコミュニケーションが密になれば、お互いが悩みを打ち明けられる環境を整えることも可能です。
治療と仕事の両立を支援
ライフワークバランスだけでなく、治療と仕事との両立を支援することも重要です。
既に疾患を抱えている人の場合、傷病休暇を通院に利用できるようにするなどの施策がおすすめです。
また、休暇を取りやすい雰囲気を構築できるかも重要なポイントとなります。

まとめ

健康経営は、従業員などの健康管理を経営的な視点で考えて、戦略的に実践する取り組みです。
企業理念に基づいた取り組みとなり、従業員への健康投資を行うことで従業員の活力向上や生産性の向上につながります。
その結果として、業績向上や株価向上につながることも期待できるでしょう。
しかし、健康経営にもデメリットがあり、成果がみえにくかったり従業員からの協力を得にくい場合があったりする点が挙げられます。
メリットとデメリットをしっかりと把握して、健康経営に取り組むべきかを判断しましょう。