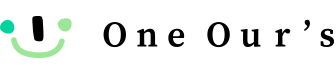投稿日:2025年08月20日/更新日:2025年08月20日
サプライチェーンとはどのような考え方?メリット・デメリットや具体例を紹介

2011年に発生した東日本大震災では、日本だけでなく世界中のサプライチェーンに大きな影響を及ぼしました。
ニュースでは頻繁にサプライチェーンという言葉を耳にするようになり、広く浸透した印象があります。
サプライチェーンについて、実際にどのようにマネジメントしていけば良いか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか?
本記事では、サプライチェーンとはどのような考え方なのか、サプライチェーンマネジメントを行うメリットとデメリットなどを解説します。

サプライチェーンとは

普段目にしたり実際に使用したりしている商品や製品の大半は、さまざまな原材料や部品などをベースとして製造されています。
また、小売店などで販売されて消費者の手元に届けられています。
農産物や海産物といった一次産品の場合も、生産者から消費者の手に届くまでのプロセスにおいて、さまざまな商流や物流があるのです。
商品や製品が消費者の手元に届くまでの間にある、調達や製造、在庫管理、配送、販売、消費などの一連の流れのことを、サプライチェーンと呼ばれています。
一連の流れにおいては、受注や発注、入庫や出庫が繰り返されますが、この取引のサイクルが鎖(チェーン)に見立てられるため、サプライチェーンと呼ばれているのです。

サプライチェーンマネジメントとは?

サプライチェーンに付随するものとして、サプライチェーンマネジメント(SCM)があります。
サプライチェーンマネジメントとは、原材料のサプライヤーから消費者までの間において、サプライチェーン全体をマネジメントすることを指す言葉です。
具体的には、サプライチェーン全体でものや金、情報の流れをシェアして、連携しながら全体の最適化を図る手法です。
各企業が連携し、個別のプロセスが最適化されるだけでなく、全体最適を図る手法として注目されています。
サプライチェーンマネジメントにより、以下の改善を図ることが可能です。
- 在庫削減
- リードタイム短縮
- 納期遵守率の向上
ただし、すべての企業で上記の効果を得られるとは限りません。
企業は利益を効率よく生み出すために適切な投資を実行し、無駄のない調達や生産が要求されます。
サプライチェーンマネジメントを導入することで、SDGsの目標達成にも寄与します。
特に、SDGsの以下2つの目標がサプライチェーンに密接に関係します。
- 目標12「つくる責任 つかう責任」
- 目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」
サプライチェーンマネジメントを取り入れるメリット

サプライチェーンマネジメントを採り入れることで、主に以下のメリットがあります。
- 消費者のニーズを把握可能となる
- リードタイムを短縮できる
- 最適な在庫管理が行える
- コストを削減に繋がる
- 生産性を向上できる
各メリットの詳細について、解説します。
消費者のニーズを把握可能となる
サプライチェーンマネジメントは、自社だけでなくサプライチェーン全体を見ながら対応する必要があります。
製造や物流、販売の情報を加味して分析する必要があり、これによって消費者が商品やサービスに対してどの程度のニーズがあるのかを把握できます。
企業間で消費者のニーズを把握すれば、状況に合わせた柔軟な対応を図ることが可能です。
また、受注数の多い商品が把握することで、新商品を開発するときの重要なインプット情報を得られます。
リードタイムを短縮できる
サプライチェーンマネジメントにより、商品の売上や販売に関する情報を企業間でシェアすることで、全体のリードタイムを大幅に短縮できるメリットがあります。
市場のニーズに合わせて早急に商品を供給できるようになれば、欠品を防止して販売機会の損失が発生するリスクを抑制できます。
また、顧客対応のスピードが向上し、顧客満足度を高めることも可能です。
最適な在庫管理が行える
サプライチェーンマネジメントを採り入れると、以下の情報を企業間でシェアできます。
- 発注数
- 受注数
- 在庫数
上記の情報は、最適な在庫管理を行うために必要な情報であり、活用することで在庫管理を容易に行えます。
在庫管理の適切化により、原材料の調達や商品の製造のプロセスで必要以上の在庫を削減することに繋げられます。
コスト削減に繋がる
サプライチェーンマネジメントの導入により商品の在庫情報を共有すれば、コスト削減に繋げられるメリットもあります。
消費者の需要を予測することで、過剰な商品の製造を抑制して在庫数が増えるリスクも減らして余計なコストを増えることを防止できます。
仕入れ先の在庫状況を監視し、納品者が自動で必要分を補充する仕組みを構築すれば、業務効率が格段に向上するでしょう。
生産性を向上できる
サプライチェーンマネジメントにより在庫管理やコスト削減を実現することで、企業間の生産性を向上できます。
商品の在庫数やニーズに対して、最適な人材配置が可能となります。
これによって、企業のリソースを最小限に抑えた生産可能となるのです。
サプライチェーンマネジメントを取り入れるデメリット

サプライチェーンマネジメントを取り入れても、必ずしもメリットばかりではありません。
以下のようなデメリットがあることを理解した上で、導入を進める必要があります。
- 企業間の統一が難しい
- 運用コストを加味する必要がある
- 万が一のトラブル対策が必要となる
- 商品開発時に視野が狭まるケースがある
各デメリットの詳細は、以下のとおりです。
企業間の統一が難しい
サプライチェーンマネジメントを実践するにあたって、企業全体で情報共有できるかが重要です。
しかし、企業によって方針や文化が異なるのが一般的であり、全体が方向性を統一することは困難です。
各企業で担当者を決めて、企業間で円滑にコミュニケーションを取る体制を構築できるかが、失敗しない鍵となります。
運用コストを加味する必要がある
サプライチェーンマネジメントの仕組みを導入するため、ITに関するコストなどの費用がどうしてもかかります。
企業の規模によって必要な運用コストは変化し、定着させるまでには長い時間がかかる傾向があります。
また、コスト次第では導入を断念する企業がいる場合、全体的なサプライチェーンマネジメントに取り組めない可能性もあるため注意が必要です。
万が一のトラブル対策が必要となる
サプライチェーンマネジメントでは、自然災害や製造環境など万が一のトラブルも加味した対応が必要です。
もしトラブルを想定し、その対策を講じないとトラブル発生時にサプライチェーンが寸断されてしまいます。
各企業が市場の動きや消費者のニーズなどを、常に情報共有できるかが重要となります。
商品開発時に視野が狭まるケースがある
サプライチェーンマネジメントにより得られた人気商品に関する情報は、次の新商品の開発に大きく寄与します。
一方、既存データの情報ばかりに着目しがちであり、思わぬ需要に気付けないケースがある点には注意が必要です。
潜在化したニーズを発掘するため、視野が狭くならないための対応を心がけてください。
サプライチェーンマネジメントで成功した事例3選

実際に、サプライチェーンマネジメントを導入して成功した事例を3つ紹介します。
成功例から自社に取り入れることができる内容が含まれているケースもあるため、ぜひ参考にしてください。
セブンイレブン
セブンイレブンを含めたセブン&アイグループでは、グループ全体での環境負荷低減を図ると同時に、サプライチェーン全体において環境負荷低減に取り組んでいます。
全国のセブンイレブンで販売している、お惣菜やお弁当などについて日本デリカフーズ協同組合に委託しています。
これにより、衛生管理レベルを向上させることに成功したのです。
また、工場の発注締め時間を変更することによって、食品残渣の削減を図ることに成功しています。
さらに、日本デリカフーズ協同組合と協働して「人権尊重の取り組み」を推進する活動も展開しています。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社は、世界で最も多くの車を生産している企業です。
部品調達の側面と市場特性よってサプライチェーンマネジメントを展開しており、世界の市場で売上がアップしている特徴があります。
トヨタ自動車の中で特に有名な仕組みが、ジャスト・イン・タイム(JIT)方式です。
ジャスト・イン・タイムとは、組み立てる際に組立工場から部品が不足しそうなタイミングで、発注をかける方式のことです。
多くの製造業で取り入れられている方式であるものの、弱点として災害時に部品工場が被害を受けると生産に大きく及ぼすデメリットがありました。
そこで、部品や原材料の企業との間で密にコミュニケーションを取り、それぞれの工場を近くに建設して解消を図っています。
スギ薬局・ライオン・PALTAC
ドラッグストアを展開しているスギ薬局と大手生活用品メーカーのライオン、卸売業のPALTACが企業の枠を超え、共同でサプライチェーンマネジメントの構築に取り組み成功を納めています。
過剰在庫や返品に対して、現場主義とスピード感、オープンな連携体制を通じて、在庫の適正化によって返品の削減を実現しました。
新製品や商品の改廃情報や販売促進施策計画、店舗別の配荷数量などの情報をシェアし、発売から終売までの店頭オペレーション施策を実施しました。
その結果、売上拡大を図りつつ在庫適正化と返品削減を実現したのです。
また、オリジナルの販促ツールを導入することで売上アップに貢献しています。

まとめ

サプライチェーンの管理は、ものやサービスを提供する企業にとって重要な課題です。
サプライチェーンマネジメントによって、サプライチェーン全体にわたって情報をシェアできれば、コスト削減や生産性向上に寄与します。
ただし、サプライチェーンマネジメントを実践しようとした場合、自社だけでの取組みではなくサプライチェーンに参画している企業の協力が不可欠です。
本記事で紹介した内容を参考に、他社の協力も得ながらサプライチェーンマネジメントに取り組んでみてはいかがでしょうか?