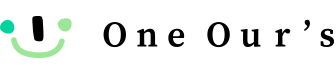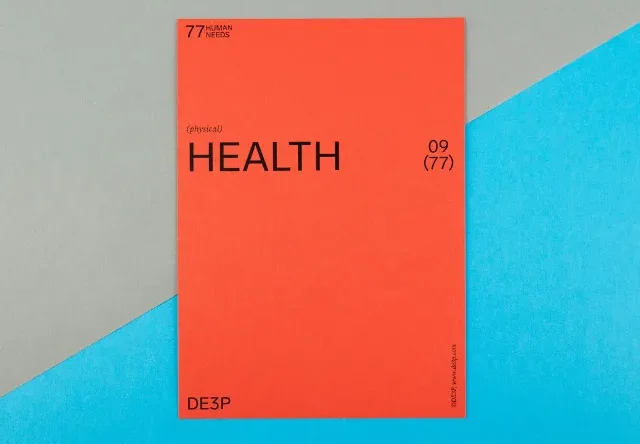投稿日:2025年08月22日/更新日:2025年08月22日
日本でも差が広まっている「教育格差」とは?子どもを取り巻く課題や世界との違い

日本では小学校と中学校が義務教育化されており、誰もが平等に教育を受けているように見えます。
しかし、実際には平等な教育を受けているとは言い難い状況にあるのが事実です。
このように、誰もが平等な教育を受けることができないことにより、教育格差が生まれています。
では、教育格差とは一体どのようなものを指すのでしょうか?
本記事では、教育格差の定義や実体、そして世界との違いについて解説します。

教育格差とは?
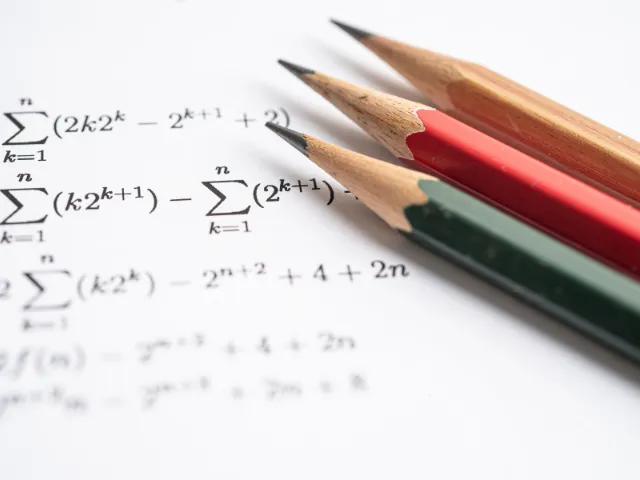
教育格差とは、社会経済的地位や生まれによって学歴が異なることを指す言葉です。
ここで定義する「社会経済的地位」とは、親の学歴や世帯収入、職業といった社会的・経済的・文化などのこと。
また「生まれ」とは出身地域などの要素を指します。
いずれも、子ども自身が変更することができない初期条件であるのが特徴です。
教育格差は深刻な問題
子どもの教育格差については、深刻な問題となっている事実があります。
1989年に国連総会で採択されている子どもの権利条約の第28条において「子どもは教育を受ける権利を保有しており、すべての子どもが小学校に通えるようにならなければならない」とされています。
子どもの権利条約は、2020年現在では196の国と地域が締約している、グローバルな条約です。
日本でも、日本国憲法第26条において以下の条文が設けられています。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
子どもの教育格差は、すべての子どもが等しく受けることができるはずの権利が侵害されている状態を指し、最優先課題として取り組むべき問題です。

教育格差が発生する5つの要因

教育格差が発生する要員として、主に以下5点が挙げられます。
- 家庭環境
- 経済状況
- 地域差
- 社会構造
- その他
各要因について、詳しく見ていきましょう。
要因①家庭環境
親の学歴や経済状況、教育への関心などが、子どもの教育機会に影響を与える傾向があります。
親が高学歴な場合、子どもにも同様の教育を受けさせてあげたいと考えるケースが多いです。
また、高学歴と年収には相関関係が見られ、学歴が高いほど一般的に年収も高くなる傾向も。
高い年収を得ていれば、子どもの教育にかける費用も増えることで教育を受ける機会も多くなります。
教育への関心も同様であり、子どもに教育を受けさせるべき親が教育に熱心でないと、自然と子どもに受けさせる教育の機会が減少します。
要因②経済状況
親の教育費の負担や学習環境の整備が不十分であったり、習い事や塾に対するアクセスを制限したりすると、教育格差が助長されがちです。
特に、教育費の負担は非常に大きな問題となります。
子どもが塾に通いたくても、それを実現できる経済的余裕が無ければ叶わないものです。
経済的な不平等が教育格差を生んで、教育格差により将来の所得格差に繋がってしまう貧困の負のスパイラルに陥ることもあります。
要因③地域差
都市部と地方を比較した場合、教育資源や学校の質の差が生まれて教育機会に格差が生じやすい傾向にあります。
具体的には、都市部では教育機関が充実しており学校設備も整っているケースが多いです。
塾や習い事といった学校以外で学習できる環境が豊富にあるので子どもは多様な学習経験を積める傾向にあります。
一方、地方の場合は学校の設備自体が不十分な場合があり、通学できる学校の選択肢も少ない場合があります。
また、塾や習い事の選択肢も少ない傾向にあるため、平等な教育を受けにくい環境となっているのです。
要因④社会構造
社会的な偏見や差別、ジェンダーによる不平等なども、教育格差を生む要因として考えられます。
特に、教育に対して男女間の格差と差別があることは問題となっています。
世界を見渡すと、小学校や中学校、高校に通うことができない女の子は、1億3200万人程度もいるのです。
これは、女の子に対する教育は不要であると考えている国や地域が、世界には数多く存在しているためです。
日本でも、大学の進学率に男女差があり、男子の大学進学率が56%程度であるのに対し、女子の場合は50%程度。
さらに、大学院への進学率をみると男子が14%程度であるのに対して、女子は5%程度と低い状況です。
このように、性別による格差により教育格差がどうしても生じてしまう傾向にあります。
さらに、日本では教育費の自己負担が一般的であるため家庭の経済状況が子どもの教育に影響を与えている点も見逃せません。
要因⑤その他
その他の要因としては、教師の質や教材、設備の不足、それぞれのニーズに対応できない教育プログラムなどが挙げられます。
また、コロナ禍によって在宅学習の環境整備の差やオンライン授業の質の格差などにより、教育格差が発生しています。

日本と世界の教育格差の違い

日本と世界とでは、教育格差に関する問題が若干異なる傾向があります。
それぞれの違いについて、詳しく解説します。
日本の教育格差
日本で生じている教育格差としては、主に以下のパターンが多くみられます。
- 学校間格差
- 家庭環境による格差
- 学歴格差
学校間格差とは、入学する学校によって受けることできる教育の質に差が原因で発生する格差を指します。
代表例として公立校と私立校の違いがあり、利用可能な施設や設備、サービスに差があります。
特に、近年整備が進んでいるICT教育については、私立校と比較して公立校の環境整備は進んでいないのが実情です。
家庭環境の格差とは、自宅における学習環境やPCなどのデバイス、学習塾などに通っているかどうかで格差が生じがちです。
実際、大学進学率などその後の学歴格差にも影響を及ぼし、その格差が経済格差とリンクしていると考えられています。
世界の教育格差
開発途上国では、教育の質のみならず教育へのアクセスが十分ではない現状があります。
ユニセフが2018年に発表した報告書によると、世界の5歳から17歳の子どもの5人に1人近くが学校に通えていない状況です。
さらに、その3分の1以上となる1億400万人が、紛争や自然災害による影響を受けています。
特に、サブサハラアフリカ地域においては、小学校に入学する年齢の子どもの中で20%程度が未就学であるとされています。
また、小学校に入学した場合でも卒業できた子どの割合は64%しかありません。
貧困家庭に育って十分な教育を受けられなかった親は、教育の大切さを理解できないケースが多い点も課題です。
国内の教育格差解消への取り組み例

日本では、経済格差を是正するために、さまざまな取り組みを行っています。
国・自治体、地域・民間団体、それぞれの支援内容を見ていきましょう。
国や自治体による支援
国や自治体による主な支援内容は、以下の4つです。
- 幼児教育・保育の無償化
- 就学援助制度
- 高等学校や高等教育への支援金・奨学金
- スクールソーシャルワーカーの配置
幼児期から、高校、大学まで、教育費の負担軽減をはじめ、給付型奨学金などで経済的なサポートを実施しています。
また、ソーシャルワーカーなどを配置することで、家庭環境に課題を抱える子どもへの支援も強化中です。
地域や民間団体による支援
地域や民間団体による支援は、多岐にわたります。
- 放課後の子供教室
- 学校外教育バウチャー
- 子ども食堂や学習支援事業
地域の空き教室などを活用し、学習・文化活動・交流の場を提供しているケースをはじめ、食事や居場所を提供する子ども食堂など、さまざま。
地域のボランティアや協賛企業、団体などによって運営されています。
個人ができる教育格差是正への取り組み

教育格差の是正は、自治体や団体レベルだけでなく、個人でも実施できます。
ここでは、個人で実施できる教育格差対策について解説します。
地域の教育支援活動へ参加する
地域の教育支援活動に積極的に参加することによって、自然と教育の質を高められます。
たとえば、地域で開催されているワークショップや講義にスタッフとして参加するなどです。
特に地域支援なら、まだ自分が知らなかった地域の歴史や文化を知れたり、地域コミュニティーの拡大やつながりの強化にもなります。
地域コミュニティーが成熟すれば、犯罪の抑止や地域活性化にもつながるでしょう。
教育支援団体へ寄付する
多くの非営利団体や教育プロジェクトに対して、寄付することによって教育格差是正に協力できます。
最近では、クラウドファンディングを通じて協力する方法もあり、協力する方法は広がっているのも特徴です。
また、NPOだけでなく中小企業やベンチャー企業などの団体に協賛する方法もあります。
社会貢献性の高い事業に賛同して、実際にサービスを利用すれば直接的な支援を行えるかが重要なポイントです。
SNSやメディアを通じた情報拡散
SNSやメディアを活用した情報拡散によって、教育格差の問題提起を行うと同時に支援を呼びかけることが可能です。
具体的には、教育に関連する課題や成功事例、支援が必要となるプロジェクトに関する情報をSNSでシェアすることにより、より多くの人に対しても問題に関心を持ってもらい行動を起こすきっかけ作りとなるでしょう。

まとめ
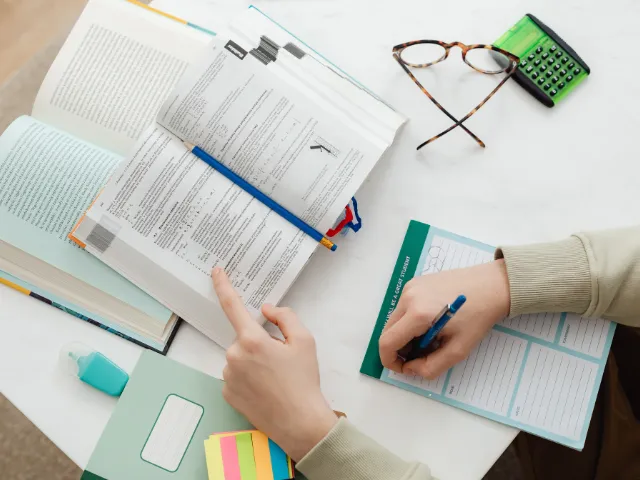
教育格差は、子どもにとっては対処できないものであり、親や周囲のサポート無くして是正できません。
様々な要因により教育格差が発生する中で、各所で支援の輪が広がっています。
また、個人でも対処できることもあるので、本記事で紹介した内容を参考に教育格差について改めて考えてみてはいかがでしょうか。