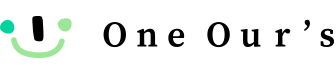投稿日:2025年08月06日/更新日:2025年08月06日
バリューチェーンとは?サプライチェーンとの違いや活用事例を紹介

最近耳にする機会が多くなった言葉として、バリューチェーンがあります。
企業にとって、バリューチェーンの手法を取り入れることで自社の強みや弱みを把握する良いきっかけとなります
実際にバリューチェーン分析を実践しようとした場合、やり方を正しく理解していなければ思うような効果を得られません。
本記事では、バリューチェーン分析の実施方法や実際の活用事例を紹介します。

バリューチェーン「価値連鎖」とは

バリューチェーン(Value Chain)とは、元々はアメリカの高名な経営学者として有名なハーバード大学経営大学院教授のポーターが提唱した考え方のことです。
バリューチェーンを日本語に直訳すると、「価値連鎖」という意味となります。
企業の事業活動として、原材料調達から製造、流通、販売を経てユーザーに商品が提供される流れが形成されています。
また、ただ販売するだけでなく、アフターサービスまで対応するのが企業側の務めとなっているのです。
それぞれの事業活動には役割や機能があって、価値を創出している側面があります。
実際に、企業が付加した価値はプロセスごとに生成された価値を単純に加算して計算した者ではありません。
互いが複雑に連鎖して、全体最適化された上で生成された連鎖(チェーン)する価値(バリュー)と捉えることができます。
一般的に、バリューチェーンは分析手法であり、内部環境を分析するフレームワークとして有効活用されています。
サプライチェーンとの相違点
バリューチェーンと似た言葉として、サプライチェーンがあります。
サプライチェーンとは、日本語に直訳すると「供給の連鎖」という意味です。
原材料の調達からスタートし、生産、加工、流通、販売に至るまで消費者にものやサービスが提供されるまでの一連の流れを指し、連のつながりを鎖(Chain)に見立てた言葉となります。
サプライチェーンは経営用語として活用されていましたが、近年ではビジネス用語として広く用いられているのです。
特に、2022年に当時の岸田総理大臣が「サプライチェーン」というキーワードを多用するようになり、言葉としての注目度が高まりました。
バリューチェーンとサプライチェーンには共通項があり、両者ともにものやサービスなどが原材料の段階から消費者に提供されるまの流れを示します。
しかし、サプライチェーンの場合はものの供給にフォーカスを当てているのに対し、バリューチェーンは付加価値に着目している違いがあります。
サプライチェーンはものを供給する流れを見える化し、供給体制の改善を図ることを目的としている考え方です。
一方、バリューチェーンの場合は製品の製造から流通、販売までの各プロセスにおいて、どのような価値が付与されているのかを見える化し、生み出す価値の最大化を図るためのものです。
また、バリューチェーンの場合は主活動と支援活動に分類できる点も大きな相違点となります。
バリューチェーンとサプライチェーンは相関関係
バリューチェーンとサプライチェーンは、お互いに影響を与え合う関係性となります。
例えば、サプライチェーンの場合は無駄な工程を省略すれば、工程の流れに変化が生じてしまいます。
生産から消費者に提供されるまでの工程が変化することで、価値連鎖の内容にも影響を及ぼします。
よって、どちらかが変化した場合は併せてリスクを分析するなどの対応が必要となるのです。
以上から、バリューチェーンとサプライチェーンは相関関係にあると言えます。
バリューチェーンを行うメリット
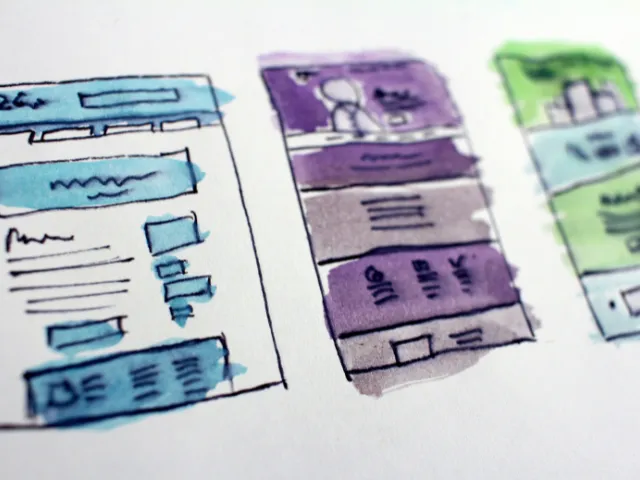
バリューチェーン分析を実施することで、以下のメリットがあります。
- コストの把握・分配ができる
- 自社を分析できる
各メリットについて、詳しく解説します。
コストの把握・分配ができる
バリューチェーン分析により、コストの把握や分析を行えるメリットがあります。
企業経営するためには、経営資源を最適な項目に配分できるかが重要です。
バリューチェーン分析を行うことで、自社の強みや弱みを履くできるため、利益に貢献している工程をピックアップできます。
そして、優先して人的リソースやコストを投入すればさらに利益を生む体質に強化できるのです。
自社を分析できる
バリューチェーン分析を活用すれば、自社を客観的に分析できるメリットもあります。
自社の状況を分析する場合、どうしても客観的に判断することが難しい場合が多いです。
バリューチェーンの分析方法
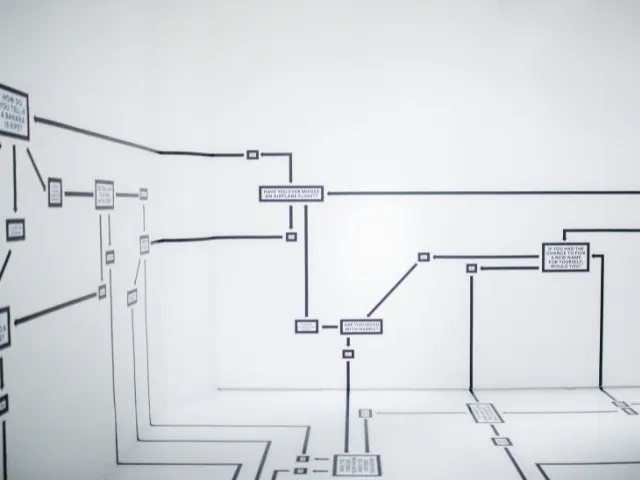
バリューチェーン分析は、主に以下のステップに沿って行えます。
- 自社のバリューチェーンを棚卸しする
- 各活動におけるコストを把握する
- 自社の強みと弱みを分析する
- VRIO分析を実施する
各ステップにおけるポイントなどを、詳しく解説します。
自社のバリューチェーンを棚卸しする
最初のステップでは、自社のバリューチェーンを棚卸して書き出しましょう。
具体的には、企業活動を工程や機能別に洗い出た上で、主活動と支援活動にカテゴライズしていく作業を行います。
バリューチェーンを棚卸する際、一連の流れに沿って書き出して自社の優位性をまとめる方法がおすすめです。
各活動におけるコストを把握する
最初のステップで棚卸したバリューチェーンをベースに、各工程や活動におけるコストをリストアップします。
コストをリスト化する際、表計算ソフトを利用すると作成しやすくおすすめです。
コストを一覧としてまとめるだけでも、コストがかかりすぎている活動をピックアップでき、気づきに繋がります。
また、特定の工程のコストを削減すると別工程のコストが増加するなどの工程や活動の関連性を把握できるメリットがあります。
自社の強みと弱みを分析する
コストを把握した後に、自社の強みと弱みを分析していきます。
主活動と支援活動の工程をベースとして、強みと弱みをリストアップしましょう。
自社の強みと弱みを分析する時に、なるべく多くの従業員にヒアリングした上で偏りがないように意見を聴衆すると良いデータを収集できます。
さらに、競合他社と比較しつつ強みを分析すれば付加価値を発見しやすくなるでしょう。
VRIO分析を実施する
最後のステップとして、VRIO分析を実施します。
VRIO分析とは、自社の競争優位性や経営資源を評価する分析手法のことで、以下の4つの要素で評価を実施します。
- Value(価値)
- Rareness(希少性)
- Imitability(模倣困難性)
- Organization(組織)
それぞれの要素に対して、YesまたはNoや点数制で回答して分析します。
各活動を要素にカテゴライズして回答することで、どの活動が自社の優位性を生み出しているかを把握できるため、経営戦略の立案に寄与できるでしょう。
バリューチェーンの活用事例

実際にバリューチェーンを活用して、改善に繋げた企業が多く存在します。
ここでは、実際にバリューチェーンを活用して改善を図った企業をピックアップして紹介します。
メルカリ
メルカリは、フリマアプリを提供しており多くのユーザーを抱えているサービスです。
メルカリでは、以下のバリューチェーンを構成しています。
- プラットフォーム構築
- 受発注機能運営
- 商品配送
- 支払い売上管理
- アフターサービス
フリマアプリであるため、ユーザーが直接売買して商品を発送し、相手とやりとりする特徴があります。
この方法により、メルカリ自体は「プラットフォーム運営」にコストを集中できる体制が整っています。
ユーザー双方が匿名状態で安心してやり取りができるシステムを開発し、ユーザー同士が安全に取引できる仕組みを構築しました。
これにより、主活動の大幅なコスト削減を実現したのです。
IKEA
IKEAはスウェーデン発のインテリアショップであり、最初は小さな通信販売会社であったものの、今では日本を含め世界中に店舗を構えています。
スタイリッシュな北欧家具が人気で、レストランが併設されている店舗もあるのが特徴です。
IKEAは、以下のバリューチェーンで構成されています。
- 設計
- 調達
- 製造
- 物流
- 販売
IKEAでは、バリューチェーン分析を行った結果より、物流に注目してコストの効率化を図りました。
従来はショップ側が実施していた商品の組み立て作業を、消費者に組み立ててもらうスタイルに変更したのです。
これによって、商品自体のサイズを小さくすることに成功し、物流プロセスにおける輸送や保管に必要なスペースを削減することに成功しています。
また、消費者自身で組み立てた家具は愛着が持たれやすい傾向があり、新たな付加価値を生む効果が生まれました。
スターバックスコーヒージャパン
スターバックスコーヒージャパンでは、バリューチェーン分析により他社との差別化を図るために導入したのが、サードプレイスの考え方です。
サードプレイスとは、自宅でも職場でもなく、第3のリラックスできる空間のことを指します。
普段生活する中で過ごす時間が多い職場や学校、家とは異なる、別の居心地の良い空間を実現したのです。
スターバックスでは、「おかえり」や「ただいま」などの声が自然と聞こえる空間となっています。
これにより、ただコーヒーを飲む場所というだけでなく、勉強や仕事目的で来店するユーザーの増加を実現しました。
まとめ

バリューチェーンは、自社の強みや弱みをしっかりと把握して、改善に繋げられる考え方となります。
競合他社の戦略を予測しつつ、先手を打つことで一歩先に進んだ対応も可能です。
経営資源の適切な配分にも寄与するなど、経営者にとってメリットが大きなものです。
本記事で紹介した内容を参考に、バリューチェーンを取り入れてみてはいかがでしょうか?