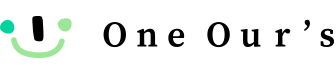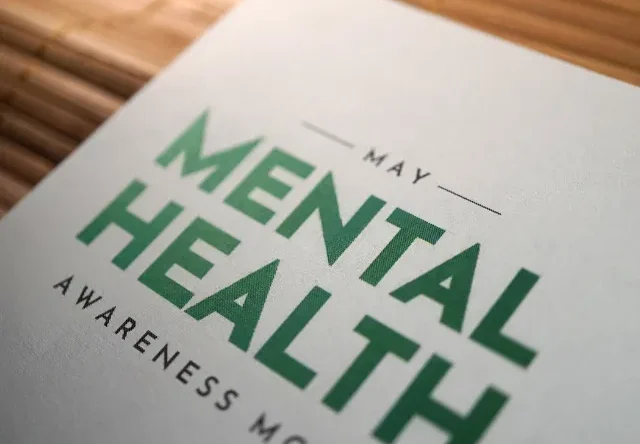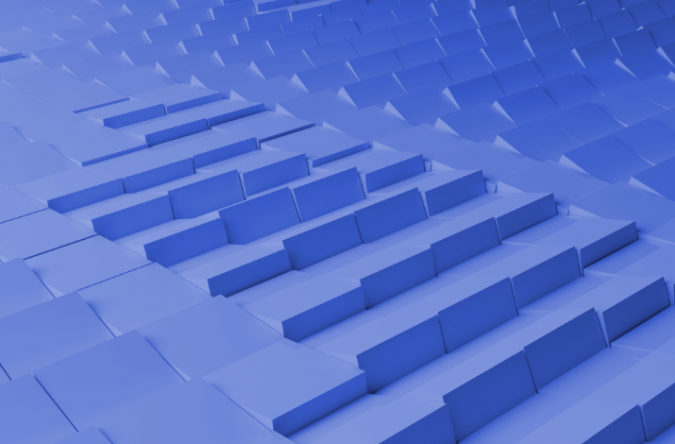投稿日:2025年07月12日/更新日:2025年07月12日
洋上風力発電とは?メリットやデメリット、今後の課題について解説

再生可能エネルギーの1つとして注目を集めている「洋上風力発電」です。
しかし、通常の風力発電とどこが違うのかと疑問に思われた人もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、洋上風力発電とは何かについてだけでなく、メリットやデメリット、今後の課題などについて解説します。
洋上風力発電に興味を持たれた人は、今回の記事をぜひ読んでみてくださいね。

洋上風力発電とは

「洋上風力発電」とは海の上に風車を設置し、風力を利用して電気を作る方法です。
基本的な仕組みは陸上の風力発電と同じで、風が風車の羽根を回すことで、回転したときに生じるエネルギーが電力に変わります。
ただし、洋上風力発電の場合、海上の安定した強い風を利用することができるので、陸上よりも効率的に電気を作ることができるのです。
洋上風力発電は、イギリスやドイツなどのヨーロッパや、中国や台湾などのアジアで導入されていますが、日本でも実現に向けた動きが活発になってきています。
また、洋上風力発電には着床式と浮体式の2種類がありますが、その違いについて以下に記載します。
| 着床式 | ・風車が海底に直接固定されている
・水深の浅い海域に設置場所が限定される ・大型の風車を設置することが可能 |
| 浮体式 | ・海面に浮かんでいる台に風車が設置される
・発電機の大きさに制約がある ・場所を選ばず大量に設置することが可能 |
近海が浅瀬になっていることから欧米では着床式が主流ですが、水深の深い日本海でも設置が可能なことから、日本では浮体式の洋上風力発電が注目されています。

洋上風力発電が注目される2つの理由

洋上風力発電が注目される理由は以下の通りです。
- SDGsの目標達成が期待されているから
- 「2050年カーボンニュートラル宣言」がおこなわれたから
それぞれについて見ていきましょう。
SDGsの目標達成が期待されているから

SDGs(持続可能な開発目標)は2030年までの国際目標で、産業界ではその業種に関係なく目標の達成が求められています。
そのため、洋上風力発電はクリーンな自然のエネルギーを利用するだけでなく、二酸化炭素を排出しないことから、SDGsの目標が達成されるのではと期待されています。
「2050年カーボンニュートラル宣言」がおこなわれたから
2020年に当時の菅首相によって「2050年カーボンニュートラル宣言」がおこなわれましたが、その中で「2040年までに最大45GWの洋上風力発電を導入する目標」が設定されました。
こうした宣言が日本で洋上風力発電の導入促進の動きを早めるきっかけとなったといわれています。
洋上風力発電の6つのメリット

洋上風力発電のメリットについてまとめてみました。
- コストの低減が期待される
- 設備の大量導入が可能
- 経済波及効果が期待される
- 漁業へのよい影響が期待される
- 国際情勢の影響を受けにくい
- 振動や低周波音の被害を受けにくい
それぞれについて見ていきましょう。
コストの低減が期待される
風力発電を効率よく行うためには、風の状態がよいことが基本条件になります。
陸上と比べて洋上は周りに障害物がないことから風の状態もよいため、コストの低減が期待されています。
設備の大量導入が可能
洋上風力発電は海上に設置されることから、騒音や景観を乱すといった心配も少なくなります。
また、場所を選ばず設置できることや、日本は周囲を海に囲まれているということから、設備を大量に導入することが可能です。
経済波及効果が期待される
洋上風力発電の設備は、数万点にもおよぶ部品が使用されていることから、こうした部品が国内で製造されるようになれば、産業の振興につながります。
洋上風力発電は、こうした関連作業による経済波及効果があるのではと期待されています。
漁業へのよい影響が期待される
洋上風力発電の基礎部分には漁礁効果(魚に取って新たな生息場となる)があり、さまざまな魚が集まってくるという報告があります。
また、日本では船が発電所内に入ることも可能なため、漁法によっては漁礁効果によるメリットもあるのではといわれています。
国際情勢の影響を受けにくい
発電に必要な石油やガスなどの資源を海外から輸入している場合、かつてのオイルショックのように、国際情勢によっては供給が不安定になることもあります。
ですが、洋上風力発電は海外に依存する必要がないことから、国際情勢の影響を受けにくいというメリットがあるのです。
振動や低周波音の被害を受けにくい
通常の山間部などにある風力発電では、近隣住人への被害問題が取りざたされていました。
羽根が回る際の振動や、低周波の音などによって、不眠やめまい、倦怠感などの被害が報告されています。
しかし、海の上に設置することで、人への被害を出すことはありません。

洋上風力発電の3つのデメリット
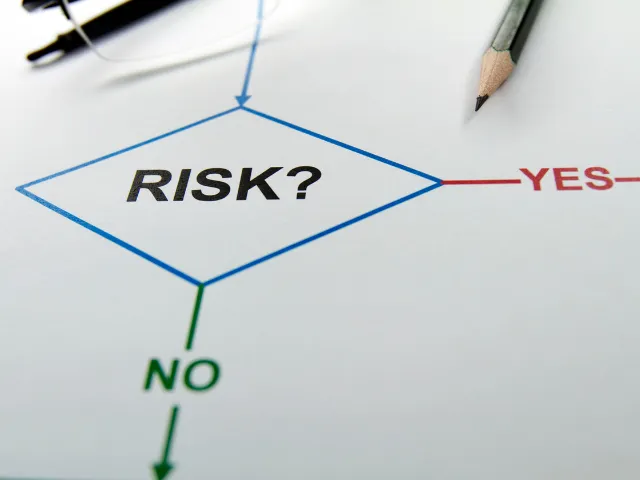
洋上風力発電のデメリットについてもまとめてみました。
- 設置やメンテナンスのコストが高い
- 生態系への影響が懸念される
- 景観が損なわれる可能性がある
それぞれについて見ていきましょう。
設置やメンテナンスのコストが高い
洋上風力発電のデメリットとして、基礎工事や海底電力ケーブルの敷設、メンテナンスなどのコストが高いということがあります。
特に海底電力ケーブルは、設置した場所が陸から離れればそれだけ長くなることから、敷設するためのコストが高くなるのです。
生態系への影響が懸念される
洋上風力発電の設置で懸念されるのは、設置工事のときの水質悪化や、稼働時の水中音による魚類や海洋生物などの生態系への影響です。
そのため、洋上風力発電を設置したことによって、海底の地盤や生態系にどのような影響があるのかという、事前の環境影響評価も不可欠になります。
景観が損なわれる可能性がある
陸上の風力発電に比べて景観を損ねる可能性は少ないですが、設置する場所によっては洋上風力発電も景観を損ねる可能性があります。
景観が損なわれたことでトラブルになることもあるので、洋上風力発電を設置する場合には、景観についてその地域に住む人との話し合いが事前に必要です。
洋上風力発電の4つの課題

洋上風力発電の課題として以下の点があげられます。
- 洋上風力発電を進めるための技術の確立
- 浮体サプライチェーンの構築
- 国内に大型風車メーカーがいない
- 建設までのプロセスが長期になる
それぞれについてもう少しくわしく見ていきましょう。
洋上風力発電を進めるための技術の確立
洋上風力発電の設置にはどのような技術が必要なのかを以下に記載します。
| ・大型風車の設置に必要な特殊な船舶や港湾設備
・洋上での設置工事 ・タワーおよび浮体の構造の強度、風車の制御のための技術開発 ・浮体構造物に関する技術開発 |
洋上風力発電を進めるためには、こうした技術の確立が何よりも必要になってくるのです。
浮体サプライチェーンの構築
2050年に必要な浮体の基数は年間800基と推算されていますが、現状ではこうした基数を製造できる浮体サプライチェーンが構築されていません。
これは浮体基礎部材全てを一貫して製造できる会社が少ないことや、浮体デザイン会社の多くがベンチャー企業であることなどが主な原因です。
ですが、洋上風力発電の導入を進めるためには、浮体サプライチェーンの確立も必要になってきます。
国内に大型風車メーカーがない
日本国内には大型風車メーカーがないため、海外から大型風車を輸入して設置するしか方法はありません。
ただし、風車のコストは全体の2〜3割程度だといわれているので、風車以外の設置工事やメンテナンスなどを国産化することで、コストの7〜8割程度は国産化が可能だといわれています。
建設までのプロセスが長期になる
ヨーロッパにくらべて日本は、プロジェクトが立ち上がって建設されるまでのプロセスが長期になるという課題があります。
日本の場合、許認可手続きが複雑で時間がかかるのですが、現在はヨーロッパのようなシステムが導入できないかどうか検討されています。
日本の洋上風力発電の導入状況

日本で洋上風力発電に取り組んでいる事例について以下にまとめました。
- 能代港・秋田港(秋田県)
- 石狩湾(北海道)
- 洋上風力発電の促進区域
- 国産化に向けた各事業者の取り組み
それぞれについてくわしく見ていきましょう。
能代港・秋田港(秋田県)

秋田県は、近海でも遠浅の海底地形が続いているなど、設置に適した環境が整っていることから、洋上風力発電が進んでいます。
秋田洋上風力発電が、丸紅を筆頭とした13社と共同でプロジェクトを進めてきた結果、2022年12月に能代港、2023年1月に秋田港で国内初の商業用洋上風力発電所が稼働しました。
総事業費は1,000億円で、4.2MW(メガワット)の風車が能代港に20基、秋田港に13基設置され、発電された電気は東北電力に充電されています。
また、秋田洋上風力発電の展示場「AOW風みらい館」には、同プロジェクトの模型や資料などが展示されています。
参照:事業概要|秋田洋上風力発電株式会社
石狩湾(北海道)

2024年1月、事業者のグリーンパワー石狩によって石狩湾で国内最大級の洋上風力発電が稼働しました。
総事業費は800億円で、日本で初めての8MWの大型風車が全部で14基設置されています。
参照:「石狩湾新港洋上風力発電所」の商業運転開始について|Green Power Investment Corporation
洋上風力発電の促進区域
洋上風力発電の促進区域は、再エネ海域利用法に基づいて指定されます。
促進区域に指定されるプロセスは以下の通りです。
| ・都道府県からの情報をもとに国が準備区域を指定
・洋上風力発電事業によって影響を受けるステークホルダー(利害関係者)を特定 ・事業について協議する法定協議会への参加の同意を求める ・ステークホルダーの同意にもとづいて有望区域に指定 ・法定協議会での調整やパブリックコメントの実施を経て促進区域に指定 |
参考:洋上風力発電の導入促進に向けた最近の状況|国土交通省
国産化に向けた各事業者の取り組み
欧州に比べると日本は洋上風力発電にかんしては遅れているのですが、政府が強力に後押しをしたということもあり、洋上風力発電に取り組む企業も増えてきています。
洋上風力発電に取り組んでいる企業は以下の通りです。
| 電力会社 | 電源開発、東京電力、JERAなど |
| 総合商社 | 丸紅、三菱商事、三井物産など |
| 再生可能エネルギー開発事業者 | 日本風力開発、グリーンパワーインベストメント、コスモエコパワーなど |
| 設備点検・メンテナンス事業者 | ホライズン・オーシャン・マネジメント |
洋上風力発電の推進には洋上風力発電事業の国産化は欠かせないことから、製造分野をはじめとする、建設から運用、メンテナンスにいたるまでの国内調達比率の引き上げが必要になってきます。
まとめ

今回は洋上風力発電とは何かだけでなく、メリットやデメリット、今後の課題や国内での取り組みなどについて紹介しました。
洋上風力発電は風力を利用することや二酸化炭素を排出しないことから、環境にとても優しい方法といえます。
また、日本は周囲を海に囲まれていることから、大量に設備を導入することができるといったメリットもあります。
その一方で、洋上風力発電の設置やメンテナンスにはコストがかかることや、技術がまだ確立されていないということは今後の課題といえるでしょう。
今回の記事を読んで洋上風力発電に興味を持たれたのなら、旅行がてらに秋田県や北海道で実際に稼働している洋上風力発電の現場を訪れてみてはどうでしょうか。