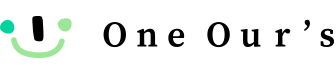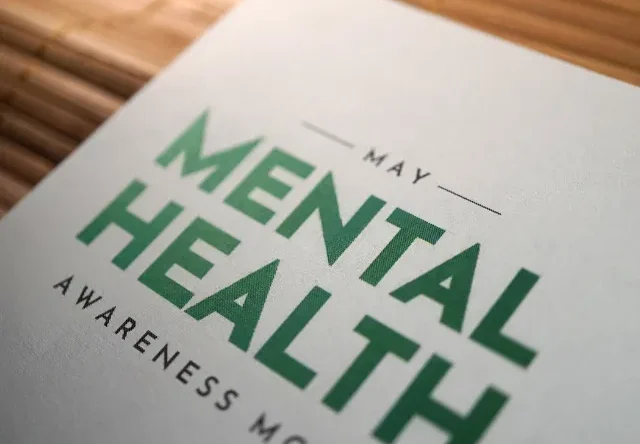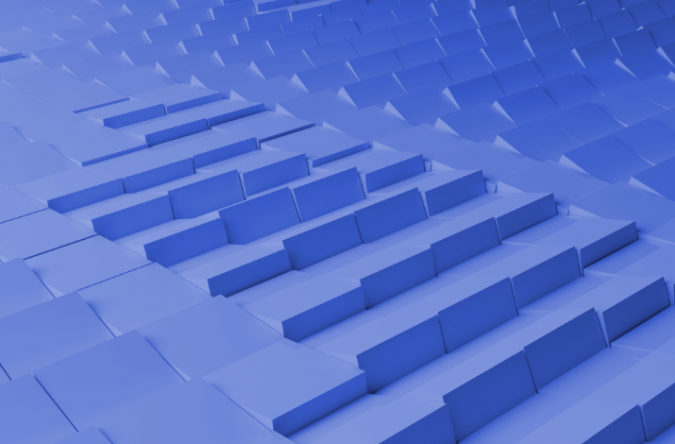投稿日:2025年05月16日/更新日:2025年05月16日
【病気になる前に防ぐ】健康に悪影響な食事の代表例9品と健やかさを保つポイント

近年、健康への意識が高まっています。
「病気になったら治す」が主流だったのに対し、現在では「病気になる前に防ぐ」がトレンド。
高齢化社会が進む中、国全体で予防医療に力を入れるようになり、毎日の食事に注目が集まっています。
本記事では、健康に悪影響な食事の代表例9品や、好影響な食事、注意点についてわかりやすく紹介します。
毎日の食事を見直し、バランスのよい食事を意識しましょう。

健康に悪影響な食事の代表例9品

日本人の健康によくないとされる食べ物は以下があげられます。
- 赤身肉、加工肉
- マーガリン
- エナジードリンク
- 砂糖を多く含む甘い飲み物
- ゼロカロリー食品
- コンビニ弁当
- 菓子パン
- ファストフード
- 高温の飲み物
それぞれ詳しく解説するため、参考にしてください。
赤身肉、加工肉
赤身肉とは牛肉、豚肉など見た目が赤い肉をさします。
加工肉はベーコン、ソーセージ、ハム、スパムといった加工して精製された肉類のことです。
赤身肉や加工肉が健康に悪影響だとされる理由は以下のとおりです。
- 発がん性リスクの高さ
- 飽和脂肪酸やヘム鉄
特に赤身肉はタンパク質が豊富で、健康によいイメージがある代表格ともいえるでしょう。
しかし、世界保健機関(WHO)の専門機関である国際がん研究機関(IARC)によると、喫煙やアスベストと同じ分類の発がん性リスクが懸念されており、特に大腸がんとの関連が指摘されています。
また、赤身肉や加工肉に多く含まれる飽和脂肪酸やヘム鉄が、動脈硬化や血圧上昇に関与するため、心血管疾患(CVD)のリスクも危惧されています。
マーガリン
マーガリンが健康に悪影響だとされる主な理由は、以下のとおりです。
- トランス脂肪酸の含有
- 心血管疾患(CVD)や炎症リスクの増加
かつてのマーガリンは、部分水素添加(硬化油)によって作られており、トランス脂肪酸が多く含まれていました。
トランス脂肪酸は、心血管疾患のリスクを高める主要な要因です。
動脈硬化の原因になりかねないトランス脂肪酸を含む製品は、多くの国で使用制限または販売の禁止が進んでいます。
ただし、現在国内で販売されているマーガリンの多くは、トランス脂肪酸を含まない製品に改良が進んでいます。
一部の安価なマーガリンやファストフード、加工食品には未だにトランス脂肪酸が含まれている場合がありますが、国内製品に関しては過剰に心配する必要はないといえるでしょう。
砂糖が多く含まれる清涼飲料水
砂糖が多く含まれる清涼飲料水(ソフトドリンク・炭酸飲料など)が健康にあたえる影響は以下のとおりです。
- 糖尿病
- 肥満
- 心血管疾患
- 歯の健康など
清涼飲料水には大量の精製糖(ショ糖・果糖ブドウ糖液糖など)が含まれます。
血糖値の急上昇を引き起こすため、2型糖尿病のリスクも考えられるでしょう。
また、過剰なカロリー摂取から高血糖・高血圧・肥満、動脈硬化や心血管疾患のリスクなどが健康への影響も心配です。
エナジードリンク
エナジードリンクは多量のカフェインが含まれており、問題視されている食品の1つです。
エナジードリンクには、1本あたり80〜300mgのカフェインが含まれています。
カフェインは身体に以下の影響をもたらすと懸念されています。
- 心拍数増加や高血圧を引き起こす可能性
- 交感神経を刺激し、不眠・不安・神経過敏を引き起こす可能性
- 睡眠障害・神経過敏に大きな影響をもたらす
- 急性カフェイン中毒のリスク
米国小児科学会(AAP)では「子供や青少年はエナジードリンクを避けるべき」と勧告しており、エナジードリンクを大量に飲むことで急性カフェイン中毒を引き起こし、不整脈・けいれん・心停止などのリスクが報告されています。
ゼロカロリー食品
ゼロカロリー食品は一見、健康に悪影響を与えるイメージは少ないかもしれません。
しかし、落とし穴があり「100mlまたは100gあたり5kcal未満」であればゼロカロリーと表示できるため、完全に0kcalではない場合もあり注意が必要です。
- ゼロカロリー飲料(ダイエットコーラ、ゼロカロリー炭酸水)
- 人工甘味料を使用した食品(シュガーフリーガム、ゼリー、ヨーグルト)
上記の食品には人工甘味料(アスパルテーム・スクラロース・アセスルファムKなど)が含まれており、これが健康に悪影響を与える可能性があると指摘されています。
長期摂取による血糖値への悪影響や、腸内環境の悪化から腸内細菌のバランスを崩す危険性、甘みへの依存を助長し過食につながる可能性が危惧されています。
そのため、ゼロカロリー食品に頼りすぎるのは危険で、適度な摂取が重要です。
コンビニ弁当
手軽で便利ですが、高カロリー・高塩分・食品添加物の多さ・栄養バランスの偏りがあり、頻繁に食べると生活習慣病のリスクが高まります。
- 高カロリー・高脂肪
- 高塩分
コンビニ弁当は揚げ物や脂質の多い食材が多く、カロリーが高めなため、肥満リスクが上昇。
また、保存性を高めるために塩分・食品添加物が多く含まれています。
食品添加物(リン酸塩・保存料・MSG)の影響で高血圧・腎臓病リスクが高まるため注意が必要です。
菓子パン
菓子パンは、高糖質・高脂肪・食品添加物が多いことが問題視されています。
白い小麦粉(精製炭水化物)と砂糖が多く使用されているため、食後の血糖値の急上昇、肥満、糖尿病、動脈硬化のリスクを高める可能性があります。
ほかにも、長持ちさせるために保存料や膨張剤(リン酸塩など)が使われていることから、頻繁に食べるのは避けた方がよいとされます。
ファストフード
手軽で美味しいファストフードも、頻繁に食べると生活習慣病のリスクが高まります。
揚げ物や脂質の多い食材が多く、カロリーが非常に高い傾向です。
そのため、高脂肪・高塩分・食品添加物の多さ・栄養バランスの偏りなどが問題視されています。
高温の飲み物
実は飲み物の温度も健康と関係があります。
約5万人を対象に行われた研究では、「70度を超える熱いお茶を飲む人は、65度以下のぬるいお茶を飲む人より、食道がんの罹患率が8倍高かった」という結果がでています。
その他にも同様の研究結果が複数存在しており、熱い飲み物が食道の内側の粘膜を損傷させ「食道がん」との関連性が高まると報告があるため、飲み物の温度にも注意したいです。

どんな食事を選べば健康によい?

では健康を意識する際、どんな食品を選べば良いかが気になりますよね。
健康によいとされる食品は以下のとおりです。
- 玄米・雑穀米
- 青魚
- 白身の肉
- 卵
- 大豆・大豆製品
- 緑黄色野菜
- 牛乳・乳製品
- 果物
- 発酵食品
- オリーブオイル
- ナッツ
それぞれ詳しく解説します。
玄米・雑穀米
玄米は白米と比べ、ミネラルやビタミンB群、食物繊維などの栄養素が豊富な食品です。
玄米は稲からもみ殻を取り除いたもので、白米よりもビタミンB1は約5倍、ビタミンEは約12倍多く含まれます。
食物繊維も豊富で、便秘を改善して腸をきれいにしてくれます。
玄米は白米に比べると消化されにくいですが、その分腹持ちがよいため、水を多めにして柔らかく炊き、しっかり噛んで食べるのがよいでしょう。
ただし、独特の臭いや食感に苦手意識を感じる方や、消化機能で不安がある方には雑穀米もおすすめです。
玄米には栄養面で劣るものの、しっかりとした栄養面が確保でき、食べやすく消化も白米とさほど変わりません。
穀米の量がメーカーによって異なるため、お気に入りの雑穀米を見つけるのも楽しいですよ。
青魚
青魚の主な成分は良質なタンパク質で、食事で補給しないと摂れない必須アミノ酸をバランスよく含みます。
「DHA(ドコサヘキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」といった体に良い油が豊富で、十分に摂ると脳の神経細胞が活性化するといわれます。
魚に含まれるオメガ3脂肪酸は心臓病予防のエビデンスが証明されており、魚の摂取量が1日60グラム増加すると死亡リスクが12%も低下したという報告もあがっています。
そのため、積極的に摂りたい食品の1つです。
白身の肉
人間に必要な栄養素の1つである、タンパク質を多く含む肉・魚類。
赤身肉は前章でも紹介しましたが、過剰な摂取は控えたい食品です。
しかし、白身肉(鶏肉)に関しては、人体への有害性は証明されていません。
肉類が好きな方、しっかりと食べ応えのある食品を好む方は、赤身肉ではなく白身肉を選択するのがおすすめです。
卵
卵はビタミンCと食物繊維以外ほとんどの栄養成分をバランスよく含む、ほぼ完全栄養食品の代表といえます。
特に良質なたんぱく質が豊富です。
ただし、コレステロール値が高くなるため、過剰に食べるのは良くありません。
バランスよく、食事に取り入れたい食品の1つです。
大豆・大豆製品
大豆製品は、体に必要なたんぱく質や脂質を多く含む、栄養価が高い食べ物です。
大豆の主な成分は良質なタンパク質で、脂質は健康にいい油とされる「不飽和脂肪酸」が含まれます。
その他にも、ミネラル、食物繊維、イソフラボンなど栄養価の高い食べ物なので、毎日食べるのがおすすめです。
ただし1日70〜75mgの摂取上限を超えないように注意しましょう。
緑黄色野菜
健康維持のためには、1日350g以上の野菜の摂取が呼びかけられています。
このうち1/3は色の濃い緑黄色野菜からの摂取が推奨されています。
色が濃いほど栄養価が高いとされ、色とりどりの緑黄色野菜は積極的に摂取したい食品です。
ビタミンやミネラル、食物繊維はもちろん、「フィトケミカル」といわれる抗酸化成分が多く含まれ、病気の予防や健康の維持が期待できます。
牛乳・乳製品
牛乳・乳製品は、良質なタンパク質やカルシウム、ビタミンB2が豊富です。
カルシウムが多く、吸収率もほかの食べ物に比べて高いのが特徴。
現代人はカルシウムが不足しがちなので、牛乳・乳製品からもしっかり摂りたい栄養素の1つです。
ヨーグルトは乳酸菌の働きにより、乳酸菌が腸内の悪玉菌の繁殖を抑えて、腸内環境を整えるのに役立ちます。
果物
果物には野菜と同様、ビタミンCやカリウム、食物繊維などが豊富です。
ビタミンCは、体にため込むことができないうえに、空気に触れたり加熱したりすると減少します。
そのため、果物のように生でそのまま食べられる食品が、非常に効果的に栄養を摂取できます。
さらにビタミンCの抗酸化作用は、メラニン色素の生成を抑え、日焼けによる肌のダメージの予防にも役立つため、夏場は意識して摂取したいです。
発酵食品
発酵食品とは、ヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆、漬物、みそなど、ビフィズス菌や乳酸菌を含むものです。
腸内環境を整え、善玉菌の効果で体の免疫機能を高め、血液中のコレステロールを低下させる働きも期待できます。
ビフィズス菌や乳酸菌は善玉菌といわれ、腸の健康を保ちます。
腸内環境を整えるためにも善玉菌を多く含む発酵食品は、日常的に摂ることがおすすめです。
オリーブオイル
オリーブオイルには、オレイン酸という体に良い油が多く含まれているのが特徴です。
オレイン酸は、善玉コレステロールを減らさず悪玉コレステロールのみを減らす働きがあり、動脈硬化の予防に役立ちます。
油を使用するなら、オリーブオイルがおすすめです。
ただし、油は開封すると酸化が始まるため、早めに使い切るよう意識しましょう。
適量は1日大さじ1〜2杯が目安です。

健康によいからといって過剰に摂り過ぎるのは良くない

ここまで「健康によいとされる食品」と「健康に悪いとされる食品」どちらも紹介しました。
しかし、健康によいとされる食べ物でも、摂りすぎると逆効果になることが分かっています。
【過剰摂取から起こりえる悪影響の例】
- 食物繊維→鉄・カルシウム・亜鉛の吸収を妨げる
- 果糖→中性脂肪の増加・糖尿病リスクが上昇
- オメガ3脂肪酸→脳出血リスクが増加
- 大豆イソフラボンの→甲状腺機能低下の可能性
逆に健康に悪影響な食品で紹介した物も、適量を意識すると問題ありません。
赤身肉はタンパク質も豊富・鉄分も取れるため、ダイエット・貧血の方にはおすすめです。
どんなに身体に良いものでも、適量を超えると健康リスクがあるため、偏りなくバランスよく食べることが重要です。
バランスの良い食事例
バランスのよい食事とは、必要な栄養素を適量ずつ摂取できることが前提です。
色とりどりの食材をバランスよく摂取することで、いろんな栄養を摂れ健康の維持ができます。
バランス
- 主食(エネルギー源) → ご飯・パン・麺類(玄米や全粒粉が理想)
- 主菜(タンパク質) → 肉・魚・卵・大豆製品(良質なタンパク質)
- 副菜(ビタミン・ミネラル) → 野菜・海藻・きのこ類(食物繊維も豊富
調味料
- 塩分 → 1日5g以下が理想(減塩醤油や出汁を活用)
- 糖分 → 加工食品・清涼飲料水を控えめに(砂糖の摂取は1日25g以下)
- 脂質 → 揚げ物を控え、良質な脂を選ぶ(オリーブオイル・ナッツ)
ストイックさもデメリットになる

健康に悪影響だからといって、すべて断ち切りストレスが貯まることもデメリットの1つです。
また、外食などでメニューに悩みすぎて食事ができないなんてことも本末転倒。
「外食だけは好きなものを食べる」や「月に〇回は好きなものを食べる」など、自分の感情やストレスをコントロールすることも、心身ともに健康に過ごすポイントです。
さまざまな食事をとることで、腸内環境のバランスも整います。
まとめ

食事は、食べてすぐに健康が害されるわけではありません。
摂取の日々の積み重ねが、病気のリスクにつながります。
食生活を見直し、常用的に摂取している人は習慣から変えるのがおすすめです。
意識をして、毎日の食事から健康を目指しましょう。