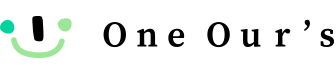投稿日:2025年04月03日/更新日:2025年04月03日
食品添加物はどれくらい危険?注意したい添加物を紹介

普段生活の中で口にしている食品を製造する過程で、食品添加物が用いられています。
食品添加物の使用により、保管期間が長くなるなどのメリットがある反面、危険なものであるとも言われています。
では、具体的にどのような理由で食品添加物が危険と認識されているのでしょうか?
本記事では、食品添加物の危険性やどのような種類があるのかについて解説します。

食品添加物とは?
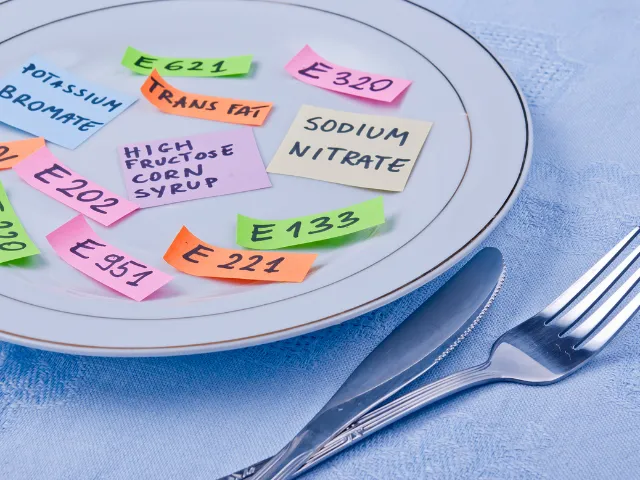
食品添加物とは、食品の製造や加工、保存の目的で食品に添加されるもので、保存料・甘味料・着色料・香料などのこと。
2015年に施行された食品表示法では、製品のラベルを見れば原材料名と添加物が判別できるように区分して表示することが義務化されました。
ただし、一括表示が認められている添加物も存在しているため、詳細まで確認できない添加物があるのが実情です。

食品添加物の役割

食品添加物を使用する目的や役割として、以下が挙げられます。
- 整った形にするため
- 品質を維持するため
- 嗜好性を向上するため
- 栄養価の補填や強化をするため
各役割について、詳しく解説します。
整った形にするため
食品添加物は、それがなければ食品ができないと言っても過言ではないほど、食品の製造や加工時に必要とされています。
例えば、食品の形を形成するために豆腐では豆腐用凝固剤を、ゼリーではゲル化剤を使用しています。
また、食感を作るために中華麺ではかんすい、チューインガムではガムベースを使用しているのです。
ほかにも、ワインに酸化防止剤を入れて熟成中の反応を防止しています。
品質を維持するため
微生物による腐敗や変敗の防止や、食中毒リスクを下げる効果もあります。
また、保存期間が短い食品の品質を保持したり、食品中の油脂などの酸化を防止して変色や変臭、過酸化物などの生成を抑制するケースも。
そのため、品質を維持するために活用しています。
嗜好性を向上するため
食品添加物は、甘味料や酸味料、苦味料、調味料、香料など嗜好性を高めるために使用されています。
特に、食品の味や香りに関するものとして、甘味料や調味料は欠かせない存在です。
また、食品に着色して視覚的に見栄えを良くするため、着色料や漂白剤、発色剤なども使用されています。
栄養価の補填や強化をするため
食品添加物は、調理や加工中に原材料の栄養成分の減少を抑える効果があります。
特に、栄養強化剤としてL-アスコルビン酸やβ-カロテン、焼成カルシウムは食品だけでなく飲料に頻繁に用いられています。

食品添加物が危険と言われる3つの理由
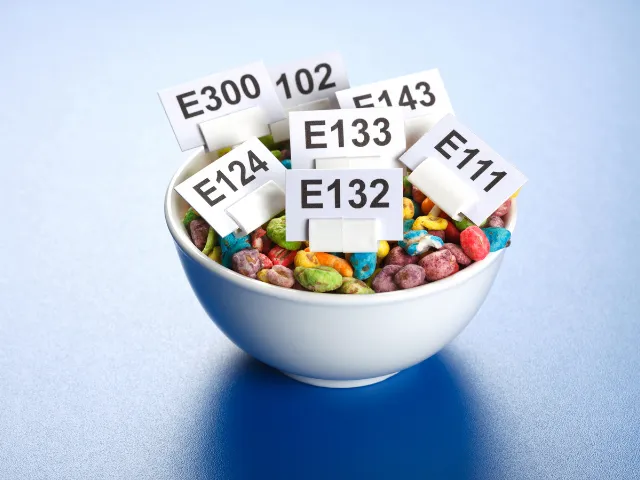
食品添加物は危険と認識されているのには、主に以下のような理由が挙げられます。
- 安全性が十分に検証されていない
- アレルギー物質が入っている可能性がある
- 糖分や脂質・塩分過多や味覚障害を引き起こすリスクがある
各理由について、詳しくみていきましょう。
安全性が十分に検証されていない
日本の食品添加物の場合、原則厚生労働省が安全性を認めたものだけが使用を許可されている状況です。
添加物の発がん性や毒性については、ラットを用いた動物実験によって安全性を確認しています。
ただし、安全性の調査については添加物単体が対象となる、複数の添加物を同時に摂取したケースは十分に検証されていないのが実情です。
また、基本的には毎日同じ添加物を大量に食べ続けたとしても健康を害することないとされている一方で、まだ複合摂取のリスクが検証されていないため絶対に安全とは言い切れません。
アレルギー物質が入っている可能性がある
摂取しようとしている食品には含まれないものの、添加物にアレルギー物質が含まれているケースがあります。
例えば、食品添加物としてペクチナーゼを使用している場合、酵素を培養する目的で小麦などのアレルギー物質を混入しており、小麦アレルギーの人が摂取するとアレルギー反応を引き起こすリスクがあります。
また、食品添加物をたくさん取りすぎることで化学物質過敏症などを発症するリスクも高まるかもしれません。
糖分や脂質・塩分過多や味覚障害を引き起こすリスクがある
食品添加物の場合、香りや味にも大きな影響を及ぼし、意識せず摂取していると糖分や脂質、塩分を過剰摂取するリスクがあります。
最近は卵や乳、果物や魚介類といった天然由来の添加物が増加しており、ラベルや表記にアレルギー品目を記載する必要があります。
添加物の味に慣れてしまうと、本来の素材の味だけでは物足りなくなりがちです。
日本人全体が同様の感覚を覚えてしまうと、食文化の衰退につながる可能性があり懸念されます。

注意したい危険な食品添加物9選

ここでは、特に危険と認識されている食品添加物として、以下9種類を紹介します。
- 亜硝酸ナトリウム
- 甘味料アスパルテーム
- 安息香酸ナトリウム
- カラメル色素
- 加工デンプン
- グリシン
- OPP・TBZ
- カラギーナン
- タール系色素
具体的に注意すべきポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
亜硝酸ナトリウム
亜硝酸ナトリウムは、主にハムやソーセージなどで発色剤の用途で添加されています。
食肉などに含まれているアミンと結合し、ニトロソアミン類という発がん性物質に変化します。
摂取し続けるとがんになるリスクが高いと懸念されています。
亜硝酸ナトリウムを使っていないハム(株式会社ライフコーポレーションが展開するBIO-RAL製品)がおすすめです。
甘味料アスパルテーム
アスパルテームは、砂糖の約200倍もの甘さがある甘味料です。
主に清涼飲料水やアイスクリームなどで使用されています。
アスパルテームは、国際がん研究機関 (IARC) 、WHO、国連食糧農業機関 (FAO) の食品添加物合同専門家委員会において、発がん性がある可能性があるIARCグループ2Bに分類されています。
脳腫瘍や白血病などを引き起こすリスクがあると言われており、なるべく過剰摂取することを避けたい添加物。
人工甘味料不使用の商品を選ぶのがポイントです。
安息香酸ナトリウム
数ある添加物の中でも、最も危険と言われているのが安息香酸ナトリウムです。
安息香酸ナトリウムはソーセージやハムなどの食肉加工品、いくらやたらこなどの魚卵加工品に主に使用されています。
安息香酸ナトリウム自体に発がん性は認められていないものの、2006年の研究では清涼飲料水中でアスコルビン酸と反応すると、発がん性物質に変化すると言われています。
発がん性があるだけでなく、うつ症状や頭痛、記憶障害などの発症リスクがある点にも注意してください。
カラメル色素
主に炭酸飲料やカップ麺、インスタントラーメン、しょうゆ、ソースなど幅広いものに使用されているのが特徴的です。
カラメル色素はカラメルⅠからカラメルⅣまで4種類存在し、製造方法により危険性が異なります。
特にカラメルⅢとⅣの場合、アンモニア化合物を加えて製造される過程において発がん性のある物質が生成されると言われています。
ただし、表示では区別がつかないため摂取を避けることが難しいのが実情です。
加工デンプン
加工デンプンは、主にスナック菓子などに含まれている食品添加物です。
加工デンプンの11種類中、2種類がEUで乳幼児向け食品に使用を禁止されています。
これは、安全性情報の不足であることが理由となっているためです。
明確に危険性が確認されていないものの、一方で安全であるというデータも不足しているため過剰に摂取し内容が良い食品添加物と言えます。
グリシン
グリシンは、主に日持ち向上剤として弁当やおにぎり、サンドイッチなどに使用されています。
高濃度のグリシンの粉塵を吸入した場合、呼吸器が刺激されたり目や皮膚に触れると刺激 を引き起こしたりします。
また、実際の塩分よりも塩味を薄く感じる効果があり、食塩の過剰摂取につながりやすいので要注意です。
OPP・TBZ
OPPやTBZは、柑橘系の果物で頻繁に使用される防カビ剤の効果がある食品添加物です。
オレンジなどを生産するアメリカにおいては、収穫後に散布される農薬として使用されているものです。
OPPの場合、日本では農薬としての使用は禁止されている一方で、食品添加物として使用することは認められています。
長期間摂取すると、皮膚炎や内臓疾患を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。
カラギーナン
カラギーナンは、天然に存在している海藻から抽出され、とろみをつけてゼリーを固めたりするために使用されています。
カラギーナンの分解物は発がん性がある可能性がある成分とされており、アメリカでは有機食品の使用を禁止されています。
また、EUでも幼児用粉ミルクに使用することを禁止している状況です。
日本でも、組織の自主規制によって使用しないケースも増えています。
タール系色素
タール系色素は、添加すると発色が良くなり色が抜けにくい作用がある添加物の1つ。
菓子や漬物、魚介加工品、畜産加工品などに使用されていますが、毒性が指摘されたことで現在では11種類に制限されています。
以前はコールタールから化学合成されたものが主流でしたが、現在では石油性品が原材料。
ただし、動物実験において発がん性や肝機能障害、甲状腺腫瘍、赤血球減少が認められているため注意が必要です。
まとめ

食品添加物は、普段口にする機会が多い食品にも実は含まれている場合が高いです。
食品添加物が含まれているものを食べたからと言って、すぐに体に害を及ぼすものではありません。
ただし、長期間の摂取により様々な悪影響を及ぼす可能性は否定できません。
本記事で紹介した内容を参考に、食品添加物について注目してみてはいかがでしょうか?