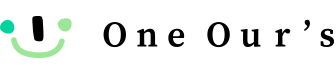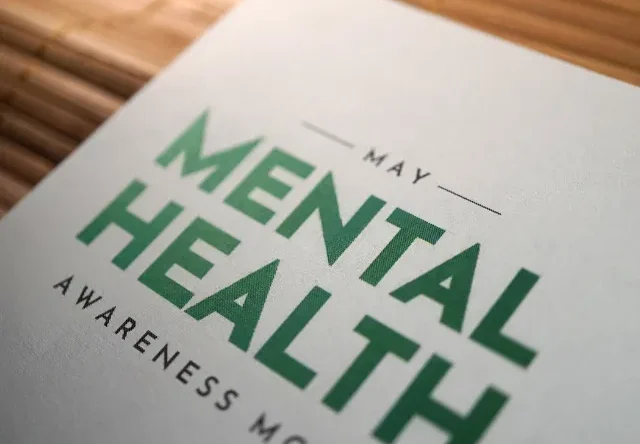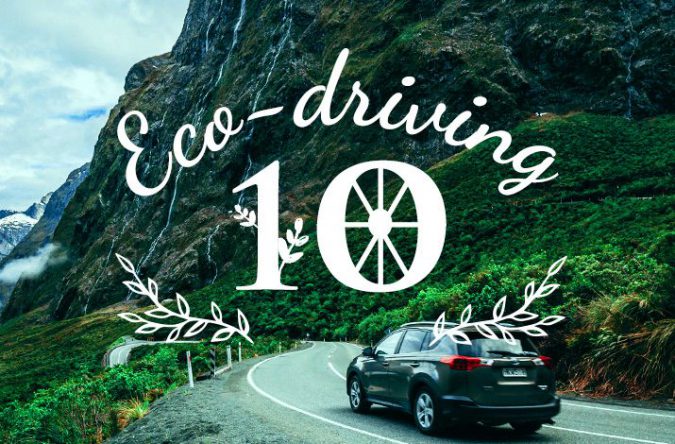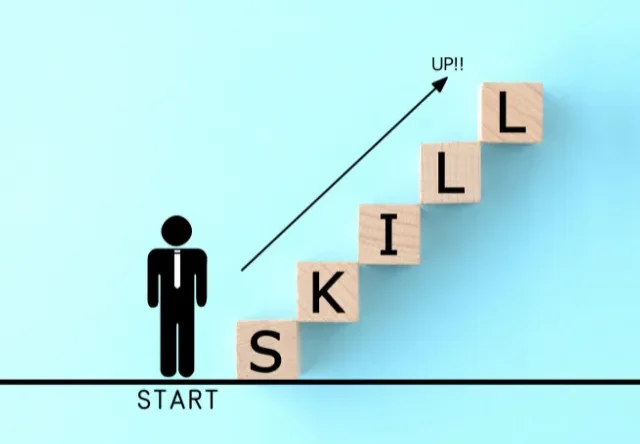投稿日:2025年08月21日/更新日:2025年08月21日
食品における「四毒」とは|体に与える悪影響と対策を紹介!

私たちが日常的に口にしている食品には、体に負担をかける可能性のある「四毒」が潜んでいます。
小麦・植物油・乳製品・甘いものを指す「四毒」は、現代の食品加工技術や生産方法の影響により、腸内環境の悪化や慢性的な炎症、アレルギー反応などを引き起こす可能性があります。
毎日の食生活を見直し、健康的な体を目指すために、四毒が体に与える影響を正しく理解しましょう。

食品における「四毒」とは

食品における「四毒」とは、以下の4つを指します。
- 小麦
- 植物油
- 乳製品
- 甘いもの
「四毒」は日常的に多くの人が摂取しているものばかりです。
現代の食品生産や食品の加工方法の影響もあり、体に負担をかける可能性が指摘されています。
それぞれの特徴や、体におよぼす影響をみていきましょう。
小麦
小麦粉に含まれるグルテンは、腸の粘膜にダメージを与える可能性があります。
グルテンは腸にこびりつき、リーキーガット症候群などの慢性的な炎症の原因を引き起こすかもしれません。
リーキーガット症候群とは、腸の防御システムがくずれて身体に有害な物質が体内に入り込む状態です。
また、小麦粉は水分を吸って固まりやすく、腸内でつまりを作ります。そのため、消化不良や便秘を引き起こし、腸内環境が悪くなるでしょう。
現代では、手軽に食べられるパンや麺類の普及により、近年では小麦製品の消費が増加しています。
植物油
植物油とは、植物から採取した油脂で、液体のものを指します。
植物油は、人間にとって大切な3大栄養素の1つである脂質の供給源です。健康維持に必要な必須脂肪酸やビタミンを含んでいます。そのため、キャノーラ油などの植物油自体が健康に有害なわけではありません。
また、消費されている植物油の多くが、以下が原因で酸敗しているのも問題のひとつです。
- 工場での加工
- 保管状態の悪さ
- 揚げ油としての繰り返しの使用による酸
現在の植物油は、高度に精製され工業的に加工された食品であるため、酸敗が怒りやすくなっています。
なお、植物油には、オメガ6が多く含まれる。オメガ6とは、体内でつくられず、食物から摂る必要がある必須脂肪酸です。
白血球を活性化する働きがあり、過剰に摂取すると、白血球が病原菌だけでなく、血管などの細胞まで攻撃し、動脈硬化を引き起こすかもしれません。
乳製品
乳製品は、動物の乳、特に牛乳を加工して作られる製品です。生乳や牛乳は加工すると固まったり粉になったりします。
乳製品は、もともとは自然の力で生まれたものでした。しかし、私たちの食生活がより豊かになるように人工的に作られたものもあります。
乳製品を摂取すると、メタボリックシンドロームの発症率が低下します。カルシウム・ビタミンD・ビタミンAなどの栄養素を効率よく摂取できるのもメリットです。
一方で、乳製品は、アレルギーの原因になりやすい食材でもあります。牛乳に含まれるカゼインは、人間の母乳に含まれるカゼインとは種類が異なり、腸管の炎症が起こりやすくなります。そのため、慢性アレルギーの原因になりやすい食品です。
なお、カゼインとは、牛乳に含まれる主要なタンパク質を指します。
また、日本人を含むアジア人は乳糖不耐症が多い傾向にあります。
乳糖不耐症とは、牛乳などに含まれる乳糖を分解する酵素であるラクターゼの働きが低いために、乳糖を消化・吸収できず、下痢や腹痛などを引き起こす症状です。
甘いもの
市販のお菓子やスイーツには、大量の精製糖質が含まれているものが多くあります。精製糖質とは、上白糖やグラニュー糖などの白い糖質です。茶色い糖質に比べて栄養が低く、エネルギーが高いため、血糖値が急上昇します。甘いものが原因の病気は、肥満や糖尿病など生活習慣病が多くあります。
精製糖質は、糖質依存症になる可能性も高めです。血糖値が急上昇すると、快感ホルモンであるドーパミンが放出され、一時的に幸せになります。その後、血糖値を下げるインスリンが大量に放出されて血糖値が急降下し、また甘い物がほしくなる。
甘いものを摂取しすぎないためには、食事以外でストレス発散しましょう。たとえば、散歩をしたり、ゆっくりとお風呂に入ったりするなど、自分の時間を作ってください。

四毒を多く含む代表的な食品と代替食

ここでは、四毒が多く含まれている食べ物を紹介します。
小麦
小麦が含まれる代表的な食品は以下の通りです。代替食とあわせて紹介します。
| 含まれる食品 | 代替食 | |
| 小麦製品 |
|
|
| 加工食品 |
|
米粉や大豆粉でつくられたパン、スイーツ、カレー粉 |
| 小麦を含む調味料 |
|
除去する必要なし |
小麦は、パンや麺などの主食だけではなく、さまざまな加工食品にも使われています。
代替食として、米粉で作られたものが考えられます。米粉とは、お米を細かくくだいて粉状にしたものです。お米は、日本人の主食であるごはんとしての食べ方が主流でした。しかし、近年では、パンやケーキ・麺などに加工した新しい食べ方が注目されています。
最近では、技術の進歩により、米粉製品や大豆粉製品も小麦粉の製品と同じくらいかそれ以上においしいものが増えてきました。
植物油
植物油は、以下の食品に含まれています。
- ひまわり油
- えごま油
- ごま油
- オリーブ油
- マーガリン
- マヨネーズ
植物油のひとつである「パーム油」は、アブラヤシの実から得られ、世界でもっとも多く使用される油です。主に以下の食品に使われます。
- インスタントラーメン
- 冷凍食品の揚げ油
- ポテトチップス
- チョコレート
なお、パーム油は、食品だけでなくシャンプーや化粧品などにも使用されます。
また、加工品は、製造過程で油脂を追加している場合が多いため、脂質を含む調味料を使いすぎないようにしてください。
たとえば、揚げものや炒めものではなく、煮物や蒸し料理を摂取すれば、調理に油を使わずにすみます。
乳製品
乳製品が含まれる食品は以下の通りです。
| 含まれる食品 | 代替食 | |
| 牛乳 | 牛乳 |
|
| 乳製品 |
|
|
| 加工食品 |
|
米粉や大豆粉でつくられたパン、スイーツ、カレー粉 |
牛乳アレルギーの原因であるたんぱく質は、乳製品によって含まれる量が異なります。たとえば、チーズには豊富に含まれますが、バターは脂質が多くたんぱく質は少量です。
なお、牛乳や乳製品を摂取しないと、カルシウムが不足しやすくなります。小魚などの食品でカルシウムを積極的に補いましょう。
甘いもの
甘いものが食べたくなった場合は以下のものを食べましょう。
- フルーツ
- ナッツ類
- せんべい
- さつまいも
なお、おやつの摂取は1日の総摂取カロリーの1割ほどが目安です。
活動レベルが「ふつう」の成人の総摂取カロリーの目安を以下にまとめます。(厚生労働省|一日に摂取する適正なカロリー(適正カロリー) は)
【女性】
| 年代 | 総摂取カロリー(kcal) |
| 20代 | 2,050 |
| 30代・40代 | 2,000 |
| 50代・60代 | 1,950 |
【男性】
| 年代 | 総摂取カロリー(kcal) |
| 20代 | 2,650 |
| 30代・40代 | 2,650 |
| 50代・60代 | 2,400 |
総摂取カロリーは、活動レベルによって異なります。「ふつう」の基準は以下の通りです。
- 座位中心の仕事か、職場内での移動や立ったままの作業・接客などがある
- 通勤・買物・家事・軽いスポーツなどの動作がある
活動レベルが「ふつう」の成人がおやつに摂取できるのは200kcalほどです。たんぱく質が豊富で食物繊維を摂れるものを摂取すると満足感が高まります。
「食品の四毒」が問題視されている理由

四毒抜きの考え方は、歯科医師の吉野敏明氏が提唱しました。四毒抜きとは、小麦・乳製品・植物性油・甘いものを排除して健康的な体を目指す考え方です。
吉野氏によると、病気の人や体調不良の人には四毒を食べている共通点が見られました。患者や吉野氏自身が四毒抜きを実践した結果、体調がよくなった人が増えました。
また、吉野氏は次のもの(五悪)を摂らない食事法も提唱しています。
- 食品添加物
- 農薬
- 化学肥料
- 除草剤
- 遺伝子組換え食品
なお、テニスプレイヤーのノバク・ジョコビッチ選手はグルテンフリーを公言しています。ジョコビッチ選手は、セルビア人の栄養士イゴール・チェトイェビッチ博士のアドバイスでグルテンフリーを実践しました。その結果、体調がよくなり、テニスのパフォーマンスが飛躍的に向上しています。
四毒を無理なく減らすコツ

四毒を無理なく減らすには自炊が1番よいでしょう。
ただし、四毒を完璧に避けようとすると挫折しやすくなります。外食や人付き合いの場では多少はOKとわり切るのもポイントです。「朝食だけ」「家で食事をするときだけ」とバランスよく実践しましょう。
また、四毒抜きは一時的なダイエットやはやりではなく、日々の積み重ねで体を整える生活習慣です。
紙のノートや日記アプリなどを使って、食事の状況を週末に1回振り返りましょう。変化が可視化できるとモチベーションアップにもつながります。
まとめ

「四毒」と呼ばれる小麦・植物油・乳製品・甘いものは、現代人の多くが日常的に摂取している食品でありながら、体にさまざまな負担をかける可能性があります。
完全に避けるのは難しいものの、米粉製品へのおきかえや調理法の工夫、適量摂取を心がけ、無理なく摂取量を減らしましょう。
四毒抜きは一時的なダイエットではなく、日々の積み重ねによって体を整える生活習慣です。外食や人付き合いでは柔軟に対応しながら、家庭での食事から少しずつ取り組んでみましょう。
食事記録をつけて変化を可視化し、モチベーションを維持しながら健康管理を実践してください。